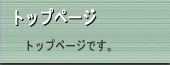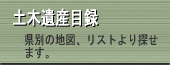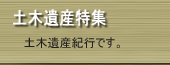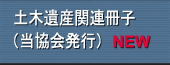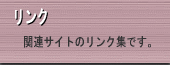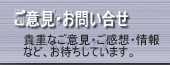第1回 九州の土木遺産の発掘について
土木遺産の調査趣意
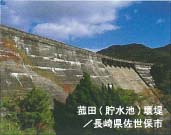 (社)九州地域づくり協会では、創立40周年の記念事業として、平成17年より3年を目途に土木遺産の発掘調査に着手しました。先人達がその時代の技術、知恵を結集し工夫、苦労されて次世代の未来の為にと築造された土木施設は、昔からも此からも社会経済活動、地域づくり、人々の日々の暮らしに貢献する歴史的な土木遺産と考え、建設の背景、先人の知恵、工夫に学び、苦労などに光を当て、分かり易くまとめて、土木遺産を一般の人々に広く知って頂き、地域の貴重な文化遺産として観光、振興に役立てて頂きたいと考えています。
(社)九州地域づくり協会では、創立40周年の記念事業として、平成17年より3年を目途に土木遺産の発掘調査に着手しました。先人達がその時代の技術、知恵を結集し工夫、苦労されて次世代の未来の為にと築造された土木施設は、昔からも此からも社会経済活動、地域づくり、人々の日々の暮らしに貢献する歴史的な土木遺産と考え、建設の背景、先人の知恵、工夫に学び、苦労などに光を当て、分かり易くまとめて、土木遺産を一般の人々に広く知って頂き、地域の貴重な文化遺産として観光、振興に役立てて頂きたいと考えています。
また、若い土木技術者を始め関係者が、仕事に誇りを持ち土木への志を奮い起こさせると共に、土木技術の啓発、継承、継続的な教育に役立てるため、公益事業の一環として調査を進めています。
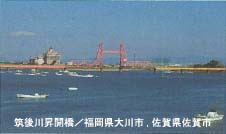 調査は、大学教授を始めとする産学官に依ります「九州の土木遺産発掘調査委員会」(委員長:樗木武 九州大学名誉教授)の基、(社)建設コンサルタンツ協会九州支部の協力を得て取り纏め、(社)九州地域づくり協会ホームページ内の「 土木遺産 in 九州 」として掲載しておりますが、今後も調査を行い充実を図って参りたいと考えております。
調査は、大学教授を始めとする産学官に依ります「九州の土木遺産発掘調査委員会」(委員長:樗木武 九州大学名誉教授)の基、(社)建設コンサルタンツ協会九州支部の協力を得て取り纏め、(社)九州地域づくり協会ホームページ内の「 土木遺産 in 九州 」として掲載しておりますが、今後も調査を行い充実を図って参りたいと考えております。
土木遺産調査の範囲対象、経緯
1) 九州の土木遺産発掘調査の範囲
① 調査の範囲、年代
九州地域にて江戸期より昭和年代までに建設された土木施設としています。
② 調査の対象
現存していて、河川、道路を主とする公共的な施設としています。
2) 調査の経緯
① 平成17年度
第一段階として、土木学会編「日本の近代土木遺産(現存する重要な土木構造物2000選)」の中より、九州での河川、道路を主とする公共的な土木施設を選出し、産学官の「九州の土木遺産発掘調査委員会(委員長:樗木武 九州大学名誉教授)」を設置して調査内容を審議を行いました。
調査は、(社)建設コンサルタンツ協会九州支部のボランティア的なご協力を得て、ホームページ掲載用として「土木遺産 in 九州」として取り纏めると共に、委員より更なる土木遺産への施設の提案を受けました。
② 平成18年度
平成17年度調査結果と共に土木遺産の評価についても、九州の土木遺産発掘調査委員会にて審議を頂き、当会のホームページに掲載し情報提供して、施設の調査を(社)建設コンサルタンツ協会九州支部のボランティア的なご協力依頼して調査をすすめました。
更に、土木遺産への施設発掘を目的として、各地の観光協会に平成17年度調査結果、平成18年度調査施設を案内して発掘提案を頂き、追加を含めて129施設の調査を行いました。
③ 平成19年度
平成18年度調査結果、土木遺産の評価方策、活用方法などについて、九州の土木遺産発掘調査委員会にて審議を頂き、土木遺産232施設(群)を当会のホームページに掲載し情報提供します。
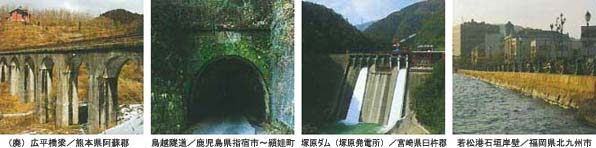
~時空を超えて、人々の暮らしの中にある土木遺産~
 先人が残した自然、歴史、文化、産業などの貴重な遺産には実に多様なものがある。そしてそれらは、学術や文化・文明の上で高く評価され、その多くが今日、観照と観賞の対象である。もちろん、本会報で紹介する近代から現代に至る土木遺産もそうした内容のものである。しかし、土木遺産は、このことに加えて今一つ大きな特色がある。それは、土木遺産が長いこと公共の福祉に寄与し、人々の暮らしの中にあって、人々の生活と活動を支え続けてきたことである。 先人が残した自然、歴史、文化、産業などの貴重な遺産には実に多様なものがある。そしてそれらは、学術や文化・文明の上で高く評価され、その多くが今日、観照と観賞の対象である。もちろん、本会報で紹介する近代から現代に至る土木遺産もそうした内容のものである。しかし、土木遺産は、このことに加えて今一つ大きな特色がある。それは、土木遺産が長いこと公共の福祉に寄与し、人々の暮らしの中にあって、人々の生活と活動を支え続けてきたことである。英知を絞って構築され、渡河、渡海の夢を実現した様々な橋。艱難辛苦の末、ようやくにして山々を克服し貫通したトンネル群。災害から生命や財産を守り、豊かな暮らしをもたらした多くのダムや河、川。人々の交流と連携を活発にし、活動を懸命になって支え続けてきた道路や鉄道、港など。これらの一つ一つが、何と多くのまちや村を築き、社会を支え、公共の福祉、人類文明の発展に貢献してきたことか。 つまり土木遺産は、人々が活動し、文明・文化を発展させる中で、人々の求めに応じて、人々の手で大地に築き上げてきた成果である。その意味で、個々の土木遺産を訪ね、観賞し、その琴線に触れることは、人々の暮らしや思い、文化の足跡をたどることに他ならない。人と人、人と社会、人と自然、人と時代など。人をベースにして巡り巡る関係の渦中に土木遺産があり、時空をこえるものである。 地域とその社会にあって、人々のために機能する土木施設は、人々に受け入れられてはじめて存在価値がある。そして、その人々は表面上の今だけに関心をもつものでない。人々は、自らが歩んできた道や経験を大切にする。その上で未来を展望し、幸せを希求するが、そうした歩みにおける現在への関心である。このことから、土木施設に関わる土木技術が真に人々の中で人々と共に歩むためには、ふるきを訪ねて新しきを知る温故知新が求められる。すなわち、土木遺産を訪ね観賞しながら、先人の知恵を理解し観照することが大切であり、身体の許す限り探勝したいと考えている。 |