第5回 水の都 佐賀 治水・利水の知恵
| わが国でも有数の穀倉地帯として知られる佐賀平野。 干満差の大きな有明海に面して、なだらかな低平地が広がる地勢により、 はるかな昔から独特の治水・利水体系が築かれてきた。 そこには水とともに生きてきた人々の叡智の証が息づいている。 |

長崎自動車道の佐賀大和ICから国道263号へ。松梅街道を南に走り、石井樋(いしいび)入口の交差点を右折すると、嘉瀬川河畔に整備された「石井樋公園」に至る。まずは公園入口の「さが水ものがたり館」へ立ち寄り、佐賀平野の風土を予習しておこう。
佐賀平野の北に連なる背振山地は山が浅く、集水力に乏しいため、広大な平野を潤すには水が足りない。唯一の大河である嘉瀬川は平野の西側を流れるため、東側では河川水が十分に利用できなかった。この難題を解決したのが、日本最古の取水施設といわれる石井樋である。嘉瀬川本流に大井手堰を設け、その上流の川幅を広げて水勢を和らげ、土砂を堰の手前に沈殿させる。その脇に設けたのが川の中央へと伸びた突堤・象の鼻と、これと向き合う突堤・天狗の鼻。この曲水路に流れを導くことで、水の勢いをさらに弱め、3箇所の井樋から土砂の少ない水を取水する。このうち石井樋からの水を東へ流れる多布施川に分流し、生活用水、農業用水として佐賀城下へ流したのである。さらに城下を洪水から守るため、二重堤防や遊水地、竹林など、巧妙な仕掛けが施されている。

この石井樋が築造されたのは、いまから約400年前。江戸初期の元和年間(1615~23)のこと。設計者は治水の名人と讃えられる鍋島藩家老の成富(なりどみ)兵庫茂安。戦国武将として幾多の築城を経験することで土木技術に精通した兵庫は、数々の水路や堤防、ため池などを築き、大小の河川やクリークを結び合わせることで、佐賀平野全体に渡る巧みな水利体系を構築したのである。
佐賀大和ICの北、嘉瀬川上流の川上峡左岸にも、兵庫が寛永2年(1625)に開削した「西芦刈水道」が残る。全長約17km。平野の南西地域に農業用水を運ぶ水路として今も現役で活躍している。兵庫は75年の生涯で100を超える治水工事を進め、今に至る郷土発展の礎を固めた。地元では“水の神様”と敬われ、現在も「兵庫まつり」が各地で行われている由縁である。
石井樋で嘉瀬川と分岐した多布施川は南流し、神野(こうの)公園の東脇を流れる。幕末の名君・直正(閑叟:かんそう)の別邸を整備した公園だが、その入口に風雅な「栴檀(せんだん)橋」が架かる。築造は大正13年(1924)。橋長16.8m、幅員5m。橋脚に荒削りの角柱石20本を用いた国内最大級の石桁橋である。その下流、佐賀城趾の北西部には「善左衛門橋」が架かる。地元の呼び名は「ぜんじゃあばし」。藩士・宇野善左衛門が度々流失する土橋を見かね、私財を投じて明和元年(1764)に架橋。橋長8m、幅員5mの石橋であり、長崎街道の要として活躍したという。このほか城趾の北東部、紺屋川に残る橋長8mの「思案橋」、東部の裏十間川に架かる「中の橋」、南部の多布施川に架かる万部島の「無名橋」など、古色を帯びた石橋群は見飽きない。

干満差が約6mという有明海に面した海岸沿いには、干拓の歴史を物語る土木遺産が残る。東与賀地区の全長1,425mの「大搦(おおがらみ)堤防」は、明治前期では最大規模の干拓堤防。川副地区の全長700mの「南西搦堤防」は明治後期に完成し、大正、昭和の干拓の基盤となったものである。
このほか周辺の見どころでは、佐賀市の北東に整備された「吉野ヶ里歴史公園」がある。弥生時代の環壕集落が大規模に復元され、卑弥呼の時代への時間旅行が楽しめる。
復元された石井樋が、治水の歴史と水の大切さを語りかける。
|
ここには小中学生が数多く見学に訪れますから、郷土の将来を担う子どもたちに佐賀の治水の歴史とともに、水の大切さを少しでも伝えていければと思っています。 |
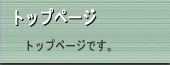
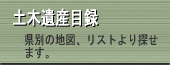
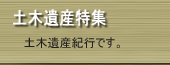
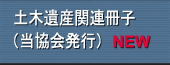
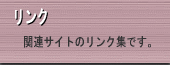
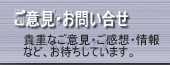


 成富兵庫が活躍した時代の鍋島藩の史料には、その業績がほとんど記されていません。約200年後に南部長恒が著した『疎導要書』によって、その存在と優れた事蹟が世に知られるようになりました。当館でも連続講座などを通じて、兵庫の優れた治水・利水事業などを紹介しています。
成富兵庫が活躍した時代の鍋島藩の史料には、その業績がほとんど記されていません。約200年後に南部長恒が著した『疎導要書』によって、その存在と優れた事蹟が世に知られるようになりました。当館でも連続講座などを通じて、兵庫の優れた治水・利水事業などを紹介しています。