めがねばし

長崎市栄町 |
 |
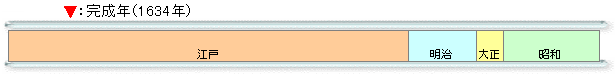
|
| 所在地・完成年等 |
施設の形式・諸元 |
●所在地:長崎県長崎市栄町 市道(中島川)
●完成年:1634年(寛永11年)
●設計者:興福寺黙子禅師
●施工者:興福寺黙子禅師
●管理者:長崎市
●文化財指定等:国指定重要文化財 |
●橋長:22.0m
●幅員:3.65(2連)
●形式:石アーチ |

|
| 遺産の説明(社会的背景・歴史的・文化的価値など) |
| 眼鏡橋は、興福寺開山唐僧黙子如定が寛永11年(1634)に架けたと伝えられます。黙子禅師は中国江西省建昌府建昌県の人で、寛永9年(1632)に日本に渡来したが、石橋を架ける技術指導者でもあったようです。2径間の半円迫持橋で、日本最初のアーチ構造の伝来とされます。正保4年(1647)洪水で崩流したというが、翌慶安元年(1648)に重修したとされ、重建とは記していないので、この崩流は昭和57年7月の長崎大水害と同程度の半壊であったみられます。以後数次の洪水にも若干の損傷がありました。長崎大水害復旧工事の際、左右両岸端部の段石が現れ、明治以前の姿に復元(昭和58年10月)されました。古来より”めがね橋”の名で長崎の人たちに親しまれていましたが、明治15年に正式に眼鏡橋と命名されました。国指定重要文化財(昭和35年2月9日指定)に指定され、370年ほど経たった今でも、観光スポットの1つともなり、市民、観光客に親しまれながら現存しています。 |
| 交通アクセス |
| JR長崎駅からは市内電車で2つ目の「公会堂前」下車
Googleマップへリンク
※当情報は位置情報のみです。施設へのアクセスが危険な箇所もありますので安全性を確認して下さい。 |