あらせばし
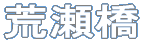
宇佐市 |
 |
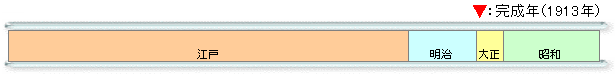
|
| 所在地・完成年等 |
施設の形式・諸元 |
●所在地:大分県宇佐市院内町副~大副
●完成年:1913年(大正2年)
●設計者:不明
●施工者:石工: 松田新之助
●管理者:不明
●文化財指定等:宇佐市指定有形文化財 |
●橋長:47.4m
●径間:14.0m(2連)
●橋高:18.3m
●橋幅:5.95m
●形式:石アーチ(凝灰岩) |

恵良川上流から望む
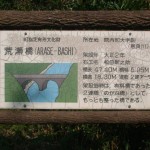
案内板 |

親柱 |
|
| 遺産の説明(社会的背景・歴史的・文化的価値など) |
宇佐市院内町は「日本一の石橋の町」といわれています。駅館川に合流する恵良川とその支流に架かる74基もの石橋は、江戸時代末期から昭和初期にかけて造られたものです。荒瀬橋は、このうち恵良川に架かる2連アーチのめがね橋で、橋高18.3mで、町内で最も水面から高い石橋です。
荒瀬橋は、大正2年という軍国主義の時代に、県の工事として架設されており、軍事的にも重要な役割を果たしていたと思われます。しかし、県では、負債が多かったため、許可を得てしばらく通行料を徴収しており、県下で最初の有料道路としても歴史的な施設です。
現在の荒瀬橋は、昭和14年に大修理が行われていますが、灯籠風の親柱など当時の面影を強く残しています。架設から95年余り経っていますが、車で通れる現役の橋として使われています。 |
| 交通アクセス |
| 宇佐別府道路院内IC下車。国道387号を南へ約7分。「道の駅」いんないに車を止めて歩いて行くこともできる。
Googleマップへリンク
※当情報は位置情報のみです。施設へのアクセスが危険な箇所もありますので安全性を確認して下さい。 |