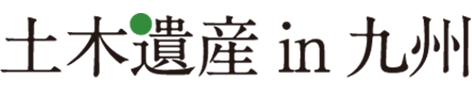FUKUOKA 27
城山三連橋
福岡県筑紫野市
九州の鉄道黎明期に造られた
のっぽの3連煉瓦アーチ橋

明治の「鉄道熱」の
情熱伝わる煉瓦造橋梁
明治14(1881)年、日本最初の私設鉄道である日本鉄道会社が創設されたのをきっかけに、九州でも私設鉄道の機運が高まり、明治16年(1883)7月4日、福岡県令によって鉄道敷設請願が行われ、明治19年(1886)以降の第1次企業勃興ブームによって全国各地から私設鉄道が請願される「鉄道熱」と呼ばれる時代が始まります。明治20年(1887)、九州鉄道発起人会は福岡、熊本、佐賀、長崎の4県連合となり、これを政府に報告。政府は、九州鉄道初代社長にアメリカ領事時代に鉄道社会学について報告
した経験がある農商務省商務局長高橋新吉を推薦しました。また、ドイツ人鉄道技師ヘルマン・ルムシュッテルを顧問技師として斡旋します。
明治21年(1888)、九州鉄道会社が設立し、翌年12月11日、博多-千歳川(ちとせがわ)仮停車場(現・鳥栖市)間で九州初の鉄道路線が開通しました。資材すべてはドイツから取り寄せ建設したといわれ、城山(きやま)三連橋は、九州鉄道の最初の着工区間(博多-久留米間)に建設された、九州で最も早い時期に造られた煉瓦造橋梁です。

市道を支える橋梁として
130年を超えて現役の廃線遺構
延長24.5m、幅4.7メートル、中央部のアーチ下には久良々川が流れ、両脇のアーチ下は道路となっています。イギリス積みで装飾はなく、橋脚部の基礎まで煉瓦でできているのが特徴です。また、川の上流側は、水圧をやわらげるために丸みがつけられています。
橋梁の北側には仮塚(かんづか)峠があり、機関車がのぼりきれないこともあり、かなり後方まで後退してまた勢いをつけ坂を上がる様は「仮塚越え」といわれていました。大正9年(1920)、二日市-原田(はるだ)間を複線化するのを機に、仮塚峠の急勾配を避けるように新線が約200mほど東へ敷設され、この区間は廃線となります。鉄道橋梁としての役目を終えてもなお、市道の橋梁として受け継がれている、九州の鉄道黎明期を物語る廃線遺構です。

DATA
所在地/福岡県筑紫野市 一般道
完成年/明治22年(1889)→道路化
設計者/ヘルマン・ルムシュッテル
文化財指定等/国登録有形文化財
<施設の形式・諸元>
煉瓦アーチ
橋長/24.5m
径間/5.5m 3連