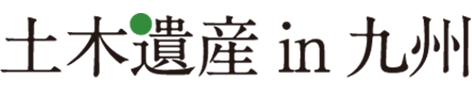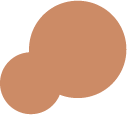
KAGOSHIMA 22
会田川暗渠
鹿児島県姶良郡湧水町米永地内
川の特性から割り出す断面
その形は防災のために

会田川の増水に備えた
防災設計
会田川暗渠(かいだがわあんきょ)は、竹下川暗渠と同じく、鉄道作業局により開通していた鹿児島線が明治36年(1903)に吉松まで開通した際に造られた暗渠です。会田川を跨ぐために造られました。
基本的には自然河川にかかるアーチと同じですが、沿線の他の暗渠と比較して内高が高いのが特徴です。これは会田川の増水に備えて、背の高い暗渠にして必要な通水断面積を確保したものと推察され、下半分より上まで石が積まれた側壁も、洪水時の水位を予測したものと思われます。

煉瓦積みの内部
急勾配の流れから
河床を護る敷石
この場所は盛り上がりが大きく、土被りが厚いので、暗渠を高くすることが可能でした。土被りが薄ければ、暗渠幅を大きくする必要があり、洪水時の出水量の詳しい計算もなく、この判断をした当時の技術水準は高いものであったことがうかがえます。
川床が比較的急勾配なため、自然石の敷石で護っているのが特徴です。

川床の敷石
DATA
所在地/鹿児島県姶良郡湧水町米永地内
JR肥薩線(栗野-大隅横川間)
完成年/明治36年(1903)
管理者/JR九州
<施設の形式・諸元>
煉瓦暗渠
煉瓦4重巻(厚47㎝)半円形
延長/29.3m 内幅/2.45m(推定)×1連
拱矢/1.23m 内高/3.7m