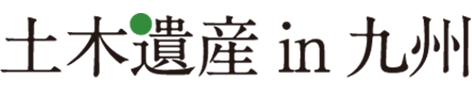NAGASAKI 16
出島橋/(旧)新川口橋
長崎県長崎市中島川河口
明治23年架橋後に移設
出島橋の名を継ぐ日本最古の鉄橋

道路トラス橋としても
日本で3番目に古い橋
出島橋は、最初は明治23年(1890)に中島川の河口に架けられ、新川口橋と呼ばれていました。明治43年(1910)に、木鉄混交橋の旧出島橋が老朽化したために、新川口橋を解体し移設。出島橋の名を受け継ぎました。
供用中の鉄橋では日本で最古、道路トラス橋としても日本で3番目に古いものです。

多くの交通量を支える出島橋
錬鉄のピン結合による
プラットトラス橋
柱と梁で出来た四角形の中に筋交いを入れ、三角形の組み合わせにすることで丈夫になる構造をトラス構造といい、この構造を組み合わせて造る橋をトラス橋と呼びます。
構造は各部材がボルトで結合されたトラスで、アメリカから輸入された錬鉄のピン結合による、斜材が「逆ハの字」のプラットトラス橋です。日本の初期の近代橋梁形式であり、歴史的視点からも貴重な橋梁で、当時の長崎の繁栄を示す近代化遺産でもあります。
平成29年(2017)に架橋され、新たな歴史を刻み始めた鉄の橋、出島表門橋からも、その姿がよく見えます。

水面に映るプラットトラス構造
DATA
所在地/長崎県長崎市中島川河口
完成年/明治23年(1890)完成→明治43年(1910)転用
施工者/日本土木会社
文化財指定等/土木学会選奨土木遺産
<施設の形式・諸元>
錬鉄プラットトラス(平行弦、ピン結合、下路)
橋長/36.7m
径間/34.75m