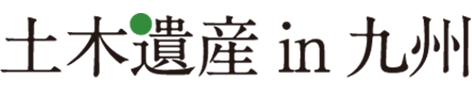OITA 41
箕ヶ谷橋、松株橋、峠橋
大分県日田市天ケ瀬女子畑
中ノ谷峠越えの沢に架かる
ドイツ人設計によるセリモチ式桁橋

別名なかぬ谷峠と呼ばれた
峠越えの難所
明治20年(1887)に、現在の国道10号とほぼ同じルートで小倉・大分間は国道35号、大分以南は国道36号になりました。
このうち、中ノ谷峠付近は、明治20年後半から30年代初めに、当時の国道36号の新設で開削されたもので、ニガキ台山地の中腹を通り、標高265mの旧野津町・弥生町の峠越えのルートで「なかぬ谷峠」と呼ばれた難所でした。

日本の石橋とは異なる構造
三段の持ち出し桁の
堅固な石組み
幅員も狭いうえにカーブが多く大型車両だけでなく、小型車の通行も容易でありませんでした。いくつもの沢があるため、橋が必要で宇藤木橋(石橋)をはじめ手の込んだ桁石橋(セリモチ式桁橋)が架設されています。
セリモチ式桁橋は、ドイツ人技師の設計によるもので、町境の中ノ谷峠より旧野津町(現・臼杵市)側に箕ヶ谷橋(みいがたにばし)、旧弥生町(現・佐伯市)側に峠橋、松株橋の合計3橋が架設されています。
写真のように上部に桁石を並べ、それを支えている持ち出し桁が三段に積まれ、上部道路面までの壁を厚くして、その重圧で持ち出し桁は迫り合い、持ち合う、堅固な石組みになっています。

DATA
佐伯市弥生大字尺間 一般道
完成年/明治30年(1897)
設計者/ドイツ人技師
管理者/臼杵市、佐伯市
文化財指定等/市指定有形文化財(箕ヶ谷)
<施設の形式・諸元>
畳石によるセリモチ式桁橋
【箕ヶ谷橋】
橋長/2.4m 橋幅/5.0m 高さ/2.5m
【松株橋】
橋長/2.5m 橋幅/5.0m 高さ/2.6m
【峠橋】
橋長/2.5m 橋幅/5.0m 高さ/2.5m