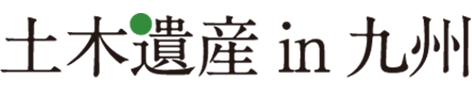OITA 48
出会橋
大分県豊後大野市清川町左右知 人道(奥嶽川)
住民総出で造った人道橋
永遠の1、2位の石橋の眺め

昭和に入っても石橋を架け続けた
石工たちの匠の技
豊後大野市清川町のほぼ中央を流れる奥嶽川(おくだけがわ)と轟川が出会う轟地区には、出会橋と轟橋(とどろばし)の2つの石橋が、径間スパン、日本1・2位とで近接して架かっています。
コンクリートや鋼鉄の橋へと転換していった昭和に入っても、石橋が架けられた大分県。「灰石(はいし)」と呼ばれる阿蘇凝灰岩の豊富な石と、中世からの仏教の石造品の歴史を背景とする石工たちの匠の技が支えていました。

谷を跨ぐ出会橋
轟橋の10年前に住民総出で架けた橋
永遠の1、2位の石橋の眺め
轟橋の下流に架かる出会橋は、径間29.3mで轟橋についで国内2位の径間スパンを誇る、単アーチ石橋です。奥嶽川(おくだけがわ)の右岸にある轟地区と左岸にある平石地区を結ぶ、人道橋として建設されました。
完成は、轟橋より10年早い大正14年(1925)で、石工は同じ山下嘉平、界寿光で、住民総出で工事を行ったと伝えられています。
深い谷を越え、2つの集落の人びとが出会うという意味もこめられたと伝わる橋の名。河川敷に降り、200年あまりの時を刻みながら、永遠の1、2位を誇る2つの橋を眺めることができる名所です。

DATA
所在地/大分県豊後大野市清川町左右知 人道(奥嶽川)
完成年/大正14年(1925)
施工者/石工 山下嘉平、界寿光
管理者/豊後大野市
文化財指定等/豊後大野市指定文化財
<施設の形式・諸元>
石アーチ(単一アーチ)
橋長32.3m
径間29.3m(日本2位)