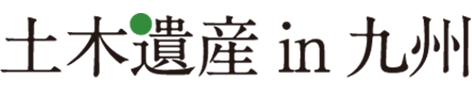OITA 08
羅漢寺橋
大分県中津市本耶馬渓町
完成当時の姿を受け継ぐ
古刹羅漢寺への参道橋

珍しい夜間工事で架けられた
耶馬溪三橋のひとつ
羅漢寺橋は、本耶馬渓町の名勝競秀峰の上流約600mのあたりに架かる雄大な石橋です。耶馬溪三橋のひとつに数えられ、耶馬渓橋、馬溪橋の完成より3年早い、大正9年(1920)に完成しました。石工は、後に石橋王と呼ばれた松田新之介です。
旧耶馬溪鉄道羅漢寺(らかんじ)駅から古刹羅漢寺への参道橋でもあったため、煌々と電灯をつけての夜間工事が珍しく、見物人も多かったと云われています。

扁平なアーチの環石
完成までに2度崩落した
至難の扁平アーチは完成時の姿
脚径間と高さの割合が5.0と扁平で、それだけに応力調節が難しく、架設も困難をきわめたようです。伸びやかな3連アーチは優美で、安定感があります。しかし、その完成までには2度におよぶ崩壊がありました。
山国川の激流にも耐え、欄干、橋桁等、今も完成当時のままの姿です。石段で河原に下りて、橋を下から鑑賞できます。

羅漢寺の仁王門
馬溪橋を渡り
石文化を知る羅漢寺と古羅漢へ
羅漢寺(らかんじ)は、14世紀開山の曹洞宗の寺院です。羅漢とは、釈迦の悟りを得た弟子達のこと。開山時には、対岸の山、古羅漢にあったと云われています。
本堂は岩山に埋め込まれたかのように建てられ、岩壁には多くの洞窟があり、無漏洞(むろどう)の五百羅漢は日本最古のもの。千体地蔵尊をはじめ、3,700体以上もの石仏が安置され、石橋とも繋がる、この地方の石文化に触れることができます。

DATA
所在地/大分県中津市本耶馬渓町大字曽木 跡田川
完成年/大正9年(1920)
施工者/竣工 永松昇、石工 松田新之助
文化財指定等/県指定有形文化財
<施設の形式・諸元>
石アーチ
橋長/89.0m 橋幅/4.5m
径間/26.25m(3連) 拱矢/4.6m